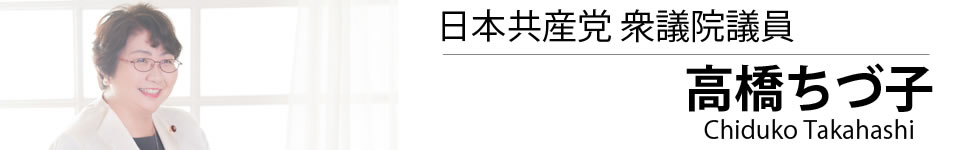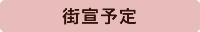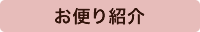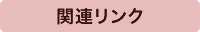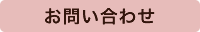助産師、医師の連携必要/高橋氏 国の支援求める
日本共産党の高橋千鶴子議員は19日、衆院厚生労働委員会で、医療法改定案に関連して、助産師と産科医の連携を国が支援するよう求めました。
高橋氏は、2006年の医療法改定では、助産師に対して妊産婦の異常時に対応する嘱託医または連携医療機関を定めるよう義務付けられたものの、断られたり、公立病院から「個人とは契約しない」といわれるなどの実態があると指摘。「助産師の個人の努力が必要とされている。(医療機関や医師にも)努力義務や協力などを担保するよう厚労省として働きかけが必要だ」と迫りました。
塩崎恭久厚労相は、「日本助産師会の医療機関と助産所の仲介、助産所への相談援助業務への財政支援などを行い、助産院と連携医療機関の確保につなげたい」と答えました。
高橋氏は、助産所2793カ所(2015年度)のうち、分娩(ぶんべん)を取り扱っているのは408カ所しかないと指摘。厚労省の神田裕二医政局長は、助産師は増えているものの、看護師や保健師業務に従事し、助産に携わっていない助産師は4万8千人中1万4千人余いることを明らかにしました。
一方、高橋氏は、この20年間で出生数は17%減少しているのに対し、分娩扱い医療機関の数は43%も減っているとして「病院、助産院のどちらも、互いの負担軽減や産前産後のケアのため、医師と助産師の連携が必要だ」と主張しました。
(しんぶん赤旗2017年5月23日付より)
――議事録――
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
今回の医療法案、実はたくさんの議題があるんですけれども、まだ議論になっていないものとして、助産院に、妊産婦等の異常に対応する病院等の名称等の説明を義務づけるということが新設されることになります。
これは、〇六年の医療法改正のときに嘱託医を義務づけた、そういう経過があったわけですけれども、それから、例えば、妊婦の状態が急変した場合についての説明ができていないことや搬送などの問題が指摘をされているわけなんですけれども、その要因について、まずどう考えているのか、お答えください。
○神田政府参考人 お答えいたします。
妊産婦に対する分娩時のリスクや、その際の管理方針については、助産業務ガイドライン、これは日本助産師会が作成しているものでございますけれども、その中において、妊産婦自身が理解できるように十分な説明を行い、その管理方針に同意を得たことが確認できる文書を作成、保存することが示されておりますけれども、妊娠中に起こり得る異常、合併症について文書を作成している助産所は半分程度、また、状態が急変した場合の医療機関への搬送や転院の可能性について文書を作成している助産所は七割という現状が明らかになっているところでございます。
また、搬送がおくれる等の事例については、助産所と医療機関の事前の情報共有や調整が不十分であるということが考えられます。
こうしたことを踏まえまして、今回の医療法改正におきましては、助産所の助産師から妊産婦に対して、分娩時のリスクや、異常の際に対応する医療機関等について書面を交付いたしまして、それに基づいて説明を行うことを義務づけることとしたものでございます。
さらに、助産所と連携医療機関との間で、日ごろから、予定される分娩等について情報共有を図るように、今回の医療法改正の成立にあわせまして、施行とあわせて周知を図っていきたいというふうに思っております。
○高橋(千)委員 当時、嘱託医を見つけるということは大変であるという指摘が随分あったと思うんですね。それが実際どうだったかということで、私も知人の助産院に改めて聞いてみたんですけれども、本当にかなり厳しかったということなわけです。約束をしていても、あるいは、よく知っている産科医がいて契約は結んだんだけれども、考えてみれば、ずっとその人がやっているわけではなくて、廃業する場合もあるわけですよね。そうなったときに、要するに何人にも断られてしまった、そういうことをお話しされていました。それがなぜなのかなということをいろいろ考えてみたんですね。
二〇〇九年の助産学会誌三月号でありますけれども、「政策と助産ケア」ということで、日本赤十字看護大学の谷口千絵氏が、これは厚生労働省の科研費を使っているんですが、「助産所開設に伴う嘱託医および連携医療機関との契約に至るまでの過程と連携の実態」という発表をされております。
これは、ああ、やはりそうだったんだと思ったんですけれども、助産師が本当に個人的に個別のお医者さんに当たって、なってくれませんかとお願いせざるを得ない、それ以外に道がないわけですね。そうすると、お医者さんからは、もう嘱託医にはならないと決めている、そういう言い方をされたり、あるいは、もう地域に公立病院しかない、仕方がないというので公立病院に頼むと、公立病院は個人とは契約しません、こういう断られ方をするんですね。ですから、もう数人以上から断られたということがあります。
そうすると、多分、イメージしているのは、いざというときに駆けつけられる、あるいは、健診を十四回、今は十四回だそうですけれども、そのうち四回ですか、行かなきゃならないわけですから、身近な医療圏の中というイメージがあったと思うんです。でも、結果として全く離れてしまう、妊産婦さんの生活圏の外に出ちゃう、とすると、そこにかかるのは大変な負担である、こういう研究結果が発表されておりました。
そこで、制度上必要なことであるにもかかわらず、産科医、医療機関への契約の義務づけはなく、助産師の個人の努力が必要とされることが示唆をされました。
私はやはりこれは本当に大事だなと思って、今提起されている、文書の作成、しっかりと事前の情報交換が大事だとおっしゃっているけれども、それをやるためにまたこういう苦労をしなければならないかもしれないんですね。そうすると、やはり、医療機関の側にとってもこれは大事なことなんだよと、義務づけとまでは言えないと思いますけれども、努力義務なり、協力しようよということを少し担保してあげる、そういう努力が厚労省に必要かなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 平成十八年の医療法の改正がございましたけれども、その際、緊急度によっては、嘱託医師の対応能力の不足などによって、委嘱医師のみでは対応が困難な状況が存在するということから、助産所の開設者は、嘱託医師に加えて、嘱託医療機関を定めるということ、それから、助産所の嘱託医師については、異常産の処理に万全を期すために、産科または産婦人科の医師に限ることなどを定めて、その施行に際しては、厚生労働省では、都道府県や産婦人科医会などの関係団体に協力を求めて、支援をこれまでも行ってはおるわけでございます。
厚生労働省として、今回の法改正の施行に際しましては、都道府県や産婦人科医会などの関係団体と連携しながら、医療機関への協力の依頼を厚労省からもする、そして、日本助産師会が行います医療機関と助産所の仲介、そして助産所への相談援助業務への財政支援などの必要な支援を行うことによって、助産所において、連携をする医療機関の円滑な確保につなげる、そういうための支援をやっていきたいというふうに思います。
○高橋(千)委員 今、財政支援ということも含めてお答えがありました。やはり、形上の、お願いしますというだけではない、踏み込んだ提案をぜひ厚労省としてやっていただきたい、このように思うんです。
やはり、我々から見ると、地域での産科医不足というのは本当に深刻なわけですね。その中で助産師外来などという知恵も出てきたわけなんですけれども、しかし、現場ではなかなか連携がとれていない。これは本当に深刻な問題ではないのかなというふうに思うんです。
さっき紹介した、同じ助産学会の中の別の資料では、妊産期から産褥期を通して、病院への搬送が必要な事例は大体一割だった、そのうち、緊急を要する事例は五%あったということなんですね。ですから、やはり日ごろの連携というのがとても大事だということと、同時に、でも九割は安全な分娩ができているんだよねと、そこも非常に大事なことではないかなと思うんです。
その上で、この最初の資料を見ていただきたいんですけれども、実は、助産師さん自体でいいますと、このように右肩上がりでふえております。ただし、就業場所というふうになっておりまして、一番多いのは病院、二万三千五百九十二人ということで一番多いわけですけれども、必ずしも助産をしているというわけではありません。
特に助産所を見た場合に、登録しているのは、平成二十七年度で二千七百九十三カ所です。そのうち、分娩を取り扱う助産所は、実はもう四百八にすぎないということなんですね。ですから、実際に就業している人も含めて、助産を行っていない人も多いと聞くけれども、厚労省としてどのように把握しているでしょうか。
○神田政府参考人 お答えいたします。
保健師助産師看護師法に基づきます業務従事者届によりまして、業務に従事する助産師は、二年ごとに、その時点で行っている業務が助産師業務なのか看護師業務なのか、また、助産所の開設者なのか従事者なのか出張助産師なのか等について届け出をしていただくこととしております。
平成二十六年末で、助産師の免許を今持っている方が約四万八千人でございますけれども、このうち、看護師業務に従事している方が一万四百五十五人、保健師業務に従事している方が三千六百八十二人ということになってございます。
○高橋(千)委員 それは要するに、引き算をすればその残りの方は、三万何がしですかね、助産をしているというお答えだったと思いますね、四万八千人のうち。
これは、実は、助産師なんだけれども内科に勤務をしている、つまり、看護師の資格を必ず持っておりますので、そういうことを聞きました。助産院をずっとやってきて、一定の年齢になって、産後ケアですとかいろいろなことで貢献をしている、そういう選び方もあると思うんですけれども、実際にそういう環境がなくなって助産をそもそもできない状況である、しかし一方では、助産師の数自体はふえている、足りているんだという議論になっちゃったら、それは困るなという問題意識を実は持ったわけであります。
それで、資料の二枚目を見ていただきたいと思うんですが、産婦人科を標榜する医療機関数と分娩取扱実績医療機関数の推移というのがあります。これは矢印が出生数ですけれども、当然ながら減っております。平成二十六年ですと百万三千五百三十九人ですが、既に昨年、百万を切っているという状況であります。また、棒グラフが、左の方は産婦人科または産科を標榜している病院と診療所、そして右の方が分娩取扱病院と診療所となると、標榜しているところのうち、実際、取扱病院というと、がくんと減るわけですね。
これは、一見すると、出生数も減っているんだから、分娩するところも減っているのは当然だろうみたいに見えるんですけれども、平成八年との比較でどのくらい減り幅が違うのかなと思ってちょっと計算してみたんですが、平成八年を一〇〇としますと、出生数は八三・二%です。分娩、病院と診療所を合わせると五七・二%と、圧倒的に分娩できる場所の方が減り幅が大きいわけなんですね。これは大変な悪循環であろう。しかも、これは全部満遍なくではないわけですから、医療圏で見るともっと深刻な事態が当然起こっていると言わなければならないと思います。
院内助産所、助産師外来など、産科医不足を補うため地方の病院はさまざまな苦労をされています。しかし、完全に医師がいなくなれば、病院での分娩はやれないわけですよね。そういう意味では、妊産婦の不安解消に助産師の活用を大いにやっていく、病院内の医師と助産師の連携、あるいは助産所と嘱託医の連携を大いにやっていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○塩崎国務大臣 今回の医療法改正で、助産師から妊産婦に対して、異常の際に対応する医療機関名等について事前に書面で交付していただいて、説明を義務づけるということによって、妊産婦の不安を解消し、そして医療機関と助産師との連携が深まって、安全な分娩が行われるということを期待しているわけであります。
こうした改正の趣旨が着実に達成されるためにも、助産師と嘱託医それから嘱託医療機関などとの円滑な連携について、国としても促進をしていくことが大事な責務だというふうに思っております。
具体的には、厚労省としては、これまで、嘱託医、嘱託医療機関との連携などを図る目的で、日本助産師会によります助産業務のガイドラインの発行を支援してまいっております。今後は、助産師会が行う医療機関と助産所の仲介、あるいは助産所への相談援助業務、これを強化するなど、必要な支援をさらに行ってまいりたいと考えております。
○高橋(千)委員 さまざま各地の取り組みを見てみたんですけれども、やはり、産科医がいなくなった、だから助産師外来というだけでは、結局、分娩までたどり着かないわけですよね。ですから、お医者さんがいるうちに、やはりきちっと連携体制をとっておくということが本当に大事なんだろう。
二〇一四年の七月十三日の読売新聞の、これは実は北海道版なんですけれども、岩手の取り組みを紹介して、北海道もこうしなくちゃねという記事がありました。
常勤医がいない県立釜石病院が院内助産をつくった。遠野市も、産科医がいなくなって、公設の助産院がいる。だけれども、大船渡の産科医がカバーをしながら、いざというときはしっかり支援をするけれども、日常的には、助産師さんの診察といいましょうか、ケアによって分娩にこぎつけるというんですかね。やはりその中で大きなメリットがあって、診察に助産師さんは長く時間をかけられる、そしてまた、ずっと、出産の直前もあるいは直後も、プロとしていろいろな不安に応えてくれる、そういう役割があるんだなということをすごく思ったんです。
そのことを北海道版でなぜ書いているかといいますと、当時、北海道は、全国平均が十万人に対して八・二人のところが、六・八人しか産科医がいない、そういう中で、やはりこういうチームの取り組みが大事だね、医師がリーダーになってチームを見守る、そういうシステムをつくればいいんだねというふうなことを提起しているんですね。
やはり、何か、助産師は安全な分娩しかやらない、産科医はハイリスクだけをやる、そういうふうに完全に役割分担しちゃうと、余りにもしんどいわけですよ。産科医というのは一番訴訟のリスクが高いわけですからね。そのリスクの高いのだけを引き受けさせられて、喜びも少なくなってしまう。そうではなくて、やはり連携をとり合って、お互いに負担も軽減になるし、支え合うことができる、そういう体制を今つくっておくことが本当に大事なんじゃないかということを重ねて提案したい、このように思っております。
そこで、もう一つのテーマなんですけれども、私がちょうど助産院にお邪魔したときに、産褥入院という表現を使っていました、産褥入院の方がいて、出産したのは一週間前なんですけれども、その後助産院に入院をしている。ちょっと、今、ナーバスになっているから静かにしようね、そういう話をしたんですけれども、その意味は非常によくわかったんですね。それは、やはり今、非常に核家族が進んでいます。両親がいない人、あるいは、いたとしても、まだ年齢が若いので働いている、なので、行くこともできないし、来ることもできない。そういう中で、たった一人で、産後、何もかもわからない中でその不安と向き合わなければならない。これを支える大事な役割を果たしているんだなということをわかったわけなんですね。
そこで、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てできる支援体制を確保するための産後ケア事業というのが二〇一五年度から始まっていると承知をしています。補助がどのようになっていて、どのくらいの実績があるのか、伺います。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
産後ケア事業、退院直後のお母さん、お子さんに対して心身のケアあるいは育児サポートなどを行って、産後も安心して子育てができる支援体制を構築する事業でございます。これは、平成二十六年度に、当時二十九市町村のモデル事業として先行実施をいたしまして、平成二十七年度以降、予算事業として本格的に進めております。
現在の予算事業におきましては、具体的に、産後ケア事業に必要な経費として、一市町村当たり約二千五百万円を上限として、その経費の二分の一の国庫補助という形にさせていただいております。これによりまして、平成二十七年度が六十一市町村、二十八年度においては百七十九市町村が国からの補助金を利用して産後ケアを実施していただいている。
また、現在、二十九年度予算では、二百四十の市町村で実施に必要な予算を確保して、事業に取り組んでいただくように支援してございます。
○高橋(千)委員 今予算を要求しているのが二百四十市町村ということで、確実にふえているなと思いますが、まだもっとふえる必要があるなというのと、これは一市町村について一律二千五百万円なので、市町村の規模によってはかなり厳しいところもあるのかなと思いますし、二分の一補助でありますので違いが出てくるのではないか、ここもよく検討していただければなと思うんですね。
資料の最後に、ことしの三月二十三日付の朝日新聞、富山の産後ケア室の記事が載っておりました。これは市の直営ということで、非常に環境もいいなというふうに思っておりますが、調べてみたら、一日、二十四時間、三食と間食も二回ついて、一万二千円のところを七千二百円の自己負担で済むんだということでありました。デイケアもあるということで、六泊七日だとすれば四万八千百円の負担だということです。
ただ、これは、今言ったように、自治体によってかなり違いがありますし、補助が足りているところもそうじゃないところもあるわけで、民間委託あるいはホテルを利用してやっている、工夫はいろいろしているんだけれども、料金がばか高いところも当然あるわけで、ばらばらになっているのかなと思います。ここがもう少し手の届く範囲になること、それから、全体に周知されていくことが必要なのかなというふうに思っております。
北海道助産師会が二〇一六年九月に産後ケア事業を立ち上げているんですが、ここは一日三千円の負担なわけですね。ただ、本当に北海道で初めて産後養生入院というのを始めた方が、当時、助産師会の会長さんで高室典子さんという方が書いているんですけれども、丸五年間行政や議会に働きかけて、なかなか産後ケアの大事さというのを理解してもらえなかった、そこから頑張った記録を書いているんです。
女性の支援には一貫したケアがやはり絶対必要なんだ、そして、妊娠、出産から子育てまで大事なんだと。そして、実際に、制度化される前に自分でやってみて聞いた言葉が、産んだ私も大事にされたいというお母さんの声ですね。ゆっくりした時間が欲しいんだと。
今食事つきと紹介したように、そうじゃないところも実はあるんですけれども、お弁当を取り寄せるところもあるんですけれども、食事つき、ですから、ゆっくりした時間、寝られる、食事が出る、そういうことによって本当に産後を大事にすることが心身の癒やしだけでなくて健全な親子関係にもつながると提起をされているんです。
これは、実は次の議論になる児童福祉法にもつながっていく非常に大事な提起だと思いますので、この産後ケアに助産師の活用というのを本当に大きく生かしていただいて、定着していくように提案をして、時間が来ましたので終わりたいと思います。
――資料――